お知らせ

千葉大学大学院医学研究院
産婦人科学講座
千葉大学病院
産科・婦人科

2007/08/31
千葉大学周産期母性科 生水真紀夫
昨年あたりから、産科・周産期医療関連のニュースがマスメディアに頻繁に取り上げられている。昨年2月に福島県立大野病院産婦人科医師の逮捕が、8月には神奈川県堀病院の看護師内診問題と奈良県大淀病院妊婦転送死亡事件が次々と報道された。
これら一連の報道を通じて、産科医療の問題点が次第に明らかになってきた。すなわち、産科医療問題は単なる医師不足ではなく、産科疾患の特殊性に加え、医療保険制度や法律などの社会制度と深く関わっていることが明らかになった。
福島県立大野病院事件では、当初産婦人科医師の初歩的な医療ミスとの見方がおおかたの報道であったかと思うが、次第に医師個人の問題ではなく産科医療に内在する不確実性や医療体制の構造的問題であるとする論調に変わった。奈良県妊婦転送事件でも、治療担当医の診断ミスや病院の受け入れ姿勢を問題視する見方が当初強かったが、次第に周産期センターを設置でききないほど医療資源が枯渇している現状が認識されるようになってきた。
産科医療は、すでに医師の自己犠牲的献身的努力では、解決できないところに近づいている。現在の周産期医療レベルを維持するには、国家・社会のサポートが必要な状況にあることが、クライアントである妊婦やその家族にも理解されつつある。
平成19年3月の「女性の健康週間」に、千葉県産婦人科学会と産婦人科医会が「いま、千葉県のお産を考える」市民公開講座を主催した。一般市民に向けて、千葉県の周産期医療の現状を伝え、周産期医療への社会的サポートの必要性を訴えるという企画であった。
筆者は、この公開講座において「産科医療の現状と問題点-大学病院の立場から-」と題して基調講演を行った。その講演要旨の一部を、本稿で紹介したい。
わが国の周産期医療は、世界トップの医療水準を保ってきた。この医療水準を以てしても、毎年50人の妊婦が死亡している。死亡した妊婦の原因を分析すると、妊婦死亡を今後さらに低下させることはほとんど不可能であると思われる。そこで、この救いきれない命があるという現実を妊婦や家族に正しく伝えておく必要がある。以下に、この点をもう少し詳しく解説する。
図1に、わが国における妊産婦死亡数の推移を示す。出生10万につき400人以上であった妊産婦死亡率は、昭和40年ころから急激に減少した。この妊産婦死亡率の低下は、産婆による自宅分娩から医師の管理する病院施設内分娩に移行した時期と符合する。したがって、医師による管理が死亡率低下に大きく貢献したと考えられる。
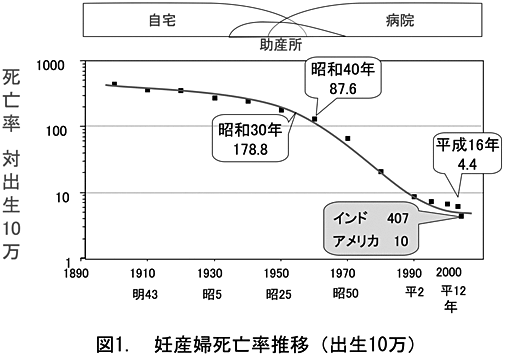
ところが、平成8年頃以降、妊産婦死亡率に低下を示さなくなった。年度ごとに多少の上下をみるが、これは妊産婦死亡数の絶対値が小さくなったためのバラツキと見なされる範囲に留まっている。
最も新しい平成17年度の集計では、全国で106万人が生まれ、62名の妊産婦が死亡した。したがって、妊産婦死亡率は出産10万あたり5.7(人)となる。平成16年度には、111万人が生まれているが、妊産婦死亡数が49名、妊産婦死亡率は4.3であった。したがって、この間妊産婦死亡の改善はみられなかったことがご理解いただけると思う。
このわが国の妊産婦死亡率は、アメリカ合衆国(10)と同等か少し低く、インド(407)より遙かに低い値である。
このように、わが国の妊産婦死亡は世界でもトップレベルの低さを誇っている。(新生児死亡率も同様で、わが国の周産期医療は世界のトップにある。)このように低い妊産婦死亡率は産科医療の輝かしい成果と考えられるものの、死亡率低下はすでに限界に近づいており、今後のさらなる妊産婦死亡率の低下は期待できないと考えられる。
最近の日本産婦人科学会の統計によると、出産250人に1人の割合で救命のための高度医療が必要となっている。そのうち99%が救命されているが、残り1%は治療にもかかわらず、大量出血や妊娠高血圧による頭蓋内出血で死亡している。救命率99%は、先に述べたように世界に誇ることのできる数字であり、産科施設の努力の成果である。しかしながら、死亡例を個別にみれば例外が存在し、救えるはずの命が失われたというケースが存在してもおかしくないがあくまで少数であろう。
分娩時の母体死亡は、極めて悲しい出来事である。五体満足に生まれてくる子供との明るい未来から、いきなり奈落の底に突き落とされる。家族・夫としては容易に受け入れられるものではない。起こりえないことが起こったのだから、医師の診断や治療技術あるいは病院の診療体制など、なんらかの原因を探そうとするのも無理はない。医師を非難することで、多少救われた気持ちになれるのかもしれない。妊娠に内在するリスクとして、あきらめるのは容易ではない。「わが国の周産期医療は、世界でトップレベルの安全なお産を実現している。それでも救えない命がある」ことを患者に理解してもらう必要がある。
妊娠して病院を訪れた患者に、「妊娠おめでとうございます。----あなたは妊娠分娩中に0.006%の確率で死にます。」と伝えるのは、後出しジャンケンの様で、いかがなものかと思う。個人的には、妊娠する前・結婚する前に(たとえば高校など)伝えておくのが最もよいのではないかと考えている。
ごく最近、裁判所外紛争処理などの厚労省関連の作業に関わっている友人と話をする機会があった。この友人によれば、高度医療にはおのずとリスクが内在しており、この点で産科医療と同様に患者教育が大切だということである。やはり、中学生か高校生くらいの時期に教育するのが望ましいと考えているようであった。
医師数は毎年順調に増加しているが、産婦人科医師に限るとすでに20年前から漸減傾向が続いている(図2)。これには、出生率低下に伴う産婦人科の沈滞ムードや医療訴訟の増加などが関与している。また、年々女性医師の比率が高まり、新規入局者の7~8割が女性となっている。その結果、分娩・育児や離職への対応が重要な問題となってきた(図3)。ここに、臨床研修制度の変更に伴う2年間のブランク(入局者なし)が加わり、マンパワー不足は一気に顕性化した。
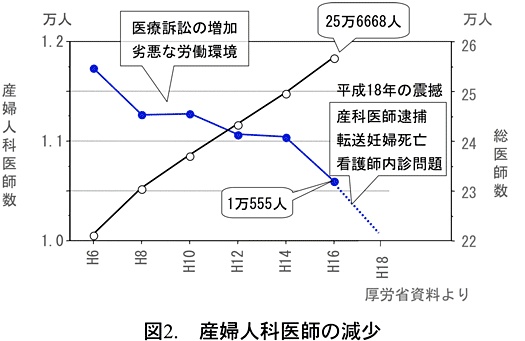
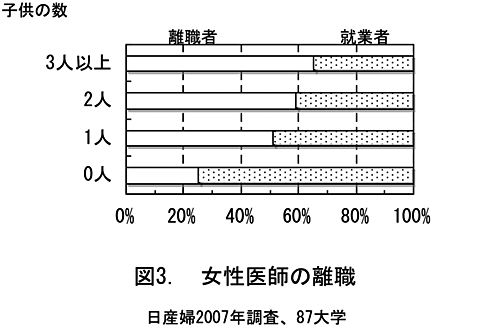
このような状況下で、先にのべた一連の産婦人科医療関連の問題が報道され、産婦人科を選択する若手医師の減少に拍車をかけた。2003年に卒業したもののうち産婦人科学会入会者は336名であったが、翌2004年卒業者では285名と30%減となった。とりわけ、男性医師の減少が顕著であった。
平成16年の統計によると、産婦人科学会員は10163名で、毎年300人のペースで減少している。このうち分娩を扱っているのは7937人にすぎず、ひとり当たりの分娩取り扱い数は139件/年である。これは、適正とされる数(120件/年)より20%過剰である。取り扱い分娩数を適正な値にするためには、産科医を1500名増やす必要がある。高齢化による自然減を考慮すると、この人数の産科医を増やすことは容易ではない。
厚労省の予測では、現在医師が不足している3臨床科(小児科、麻酔科、産科)のうち、唯一産科志望者のみが今後も減少し続けるとの予測を発表している。
週平均勤務時間の集計によると、産科医の勤務時間は69.3時間で、きわめて過酷な労働とされる宅配業よりさらに長い。ちなみに、小児科は68.4時間、外科が66.1時間で、医師平均では63.3時間である。(これらはいずれも法廷労働時間の40時間を遙かに超えており、過労死認定の目安とされる60-65時間をも超えている。)
余談ながら、労働時間が長いために時給でみたときの勤務医の収入は、看護師のそれより低いという統計がある(週間東洋経済)。この割安感も勤務医の意欲を低下させる一因となっている。
マンパワーの不足・過重労働・医療ミス・医療訴訟は、それぞれが原因となり結果となって益々状況を悪化させる(「産科医療の負のスパイラル」、図4)。
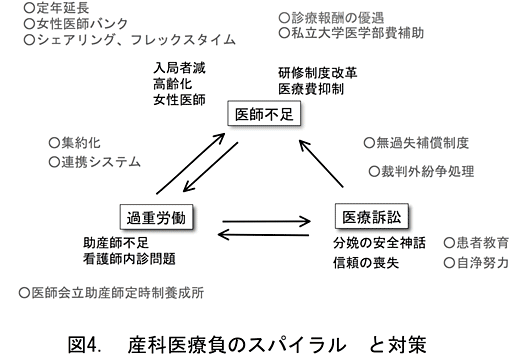
この負のスパイラルは、産科以外にも通用するスキームである。しかし、先に指摘したように、医療訴訟や看護師内診問題など多くの社会的要因や産科疾患の特殊性などが加わって、回転速度が速くなっている。以下に社会的要因のいくつかについて触れておく。
脳性小児麻痺のうち分娩時の異常に起因するものはたかだか2割で、そのうち分娩管理に問題があるとされるのは半分程度と推定される。ところが、脳性小児麻痺の原因は稚拙な分娩管理にあるとの誤った理解が広まっている。
さらに、困ったことに脳性小児麻痺に対する直接的な社会保障制度がない。このため、弱者救済的な観点から医師に保障を求める判決が出されることがある。
こどものすべてが100%健康で生まれてくる訳ではない。最高水準の産科医療を実践していても、一定の率で何らかの障害を持った子供達が生まれてくる。このような子供達を、親のみで支えていくのには無理がある。「次世代を担う社会の宝」である子供を増やすための施策をとろうとする国が、一定の率で生まれてくる障害児への対策を親にのみ負担させている現状はあまりに身勝手な施策といえよう。
看護師の内診問題も問題を複雑にしている。これは、看護師の内診は認められないとする厚生省看護課長通知によって発生した問題である。
わが国の分娩のうち、半分の50万件あまりが病院で取り扱われている。病院では、4,000人の医師と15,000人の助産師とが診療に当たっている。一方、残り50万件の分娩が、診療所で取り扱われている。この診療所では、3,000人の医師が、助産師3,000人とともに分娩管理に当たっている。したがって、診療所で働く助産師は少なく、全国で10,000人の助産師が不足している。
そこで、各地の産婦人科医会などでは、医師による診療の補助を担当してもらうための専門看護師養成コースを設置して準備してきた。助産師不足の現実にあって、より安全な分娩管理を実践するための現実的な対応策であった。このような看護師による診療補助は、アメリカで実施されていると聞く。看護師が医師をサポートすることが、患者の命を危うくすることにつながるとは考えにくいと思うがいかがであろうか。
看護師の内診が認められないとすると、医師がすべての診療行為を自ら行わねばならず、その負担は飛躍的に増加する。医師の仕事量は増加して、ますます負のスパイラルに入り込むことになる。実際、負担増から、分娩取り扱いを断念した産科医師も出てきている。
妊娠中には、常位胎盤早期剥離を始めとしてさまざまな異常が突発し、急速に進行する。対応が遅れれば母子ともに致命的となり、逆に速やかに対応できれば救命が可能である。したがって、妊婦の近くに医療施設が存在している必要がある。これまで、各地の地方自治体はおのおの分娩施設を整備し、各地で発生する救急疾患に対応してきた。この結果、地方ではいわゆる一人医長の産科医が勤務する小病院が点在することになった。
平成16年の福島県立大野病院事件では、前置胎盤のため帝王切開を受けた妊婦が死亡した。その後、平成18年2月になって、手術担当医が業務上過失致死と医師法21条違反の疑いで逮捕・刑事訴追された。前置胎盤に合併した「癒着胎盤」を無理に剥離したため、大量出血をきたして死亡させたとして、刑事責任が問われている。
この事件では、地域医療の最前線の小規模病院での一人医長制度は、医師にとっても患者にとってもリスクが高いことが示された。この事件は、地方の小規模病院から医師を引き上げる大学医局を増加させ、地域医療の崩壊」の危惧を予想より早く現実のものとする契機となった。
このような状況を打開するため、国の指導のもとで都道府県単位での医療資源の集約化(医師を一箇所に集める)が図られることになった。(しかし、いくら道路が良くなっても、車で1時間以上をかけて漸く産科診療施設にたどり着くという状況は好ましくない。このような産科の特殊性から、集約化による対応に異論をとなえるむきもある。)
平成18年には、奈良大淀病院で分娩中に意識不明となった妊婦の転送が難航するというケースがあった。奈良県内には周産期母子医療センターがなく約20の病院に転送を断られた後最終的に大阪市内の病院に収容されたが、妊婦は脳出血で死亡した。当初は、担当医の診断ミス(分娩子癇と診断)として非難するむきが強かったが、そもそも周産期医療施設が少ないうえに病院間の救急搬送システムが欠如しているなど、社会的な問題が背景にあることが次第に明らかになった。千葉県では、総合周産期母子医療センター は2箇所しかなく、人口100万当たり1施設という国の基準にはまったく達していない。奈良県とよく似た状況が、千葉においても発生する可能性があり、事実過去には類似したケースが報告されている。
救急搬送システムの整備はきわめて大切である。妊娠高血圧症から子癇発作をきたした妊婦を抱えた一人医長が、病状の急変に対応しつつ搬送先を探すのは、事実上無理である。
千葉市の周産期医療の現状について、簡単に触れておく。平成19年に千葉市医師会によって行われた産婦人科救急医療調査報告によると、千葉市には産科医療を行っている病院が6つ、開業施設が9つあり、年間およそ8000件の分娩を取り扱っている。従事する医師数は約50名であるので、医師一人当たり年間160件を取り扱っていることになる。
市内には、周産期母子医療センターに認定された施設はない。平成16年3月と平成19年1月にそれぞれ、1病院が分娩取り扱いを中止した。産科医師の51%が65歳以上と高齢化しており、すでに医師の半分が分娩取り扱いをやめている。50歳以下の医師は僅かに25%に過ぎない。
また、6病院のうち3病院は勤務医師数が4人以下となっている。10人以上が勤務しているのは、千葉大学附属病院のみとなっていて、中小規模の病院が主体となっている。
千葉大学産婦人科の入局者でみると、平成11年を境に入局者が半減してこの数年は1-3名で推移している(図5)。平成11年は、都立広尾病院や横浜市立大学などでの医療事故が報道され大学病院が批判の矢面に立たされた年である。平成11年以降は、入局者のうち女性が80%以上を占めるようになったのも大きな特徴である。医学部入学者に占める女性の割合は年々上昇していることと関連していると思われるが、産婦人科入局者に女性が多いのはある意味当然であろう。アメリカでは、女性医師(母性医師)の場合労働時間の0.3を出産や子育てに使うことを前提にしているという。したがって、マンパワーという面から見ると、女性医師のそれは男性の0.7ということになる。最近のわが国の統計では、女性医師の30%が、出産や育児を契機に離職していることから、0.7以下のマンパワーとなっていると思われる。周産や育児に対するサポートが不十分であることが大きな原因となっている。
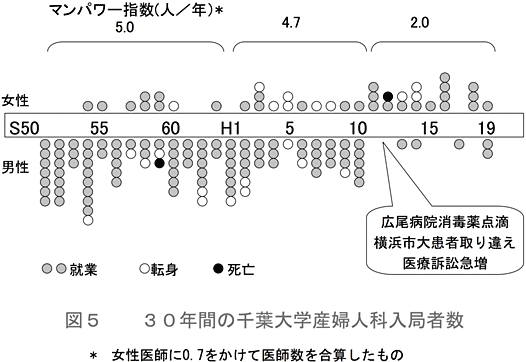
最新の図はこちら
このような厳しい状況にあって、行政もわれわれ産婦人科医も対策を取り始めた。このうち主なものを図4に記入した。
千葉県の周産期施設の重点化・集約化については、国の指示に基づいて平成18年度にワーキンググループを立ち上げて検討が行われた。集約化の中心となる千葉大学では、この数年をかけて関連病院の集約化をすでに実施しており、一部医師の移動を除いてこれ以上の集約化は困難との結論に達した。
さらに千葉県では、県内に附属病院を持つ私立大学の学生を対象に一人当たり3200万円を上限に奨学金を支給する制度を立ち上げた。この奨学金制度では、小児科もしくは産科を選択した場合、返還免除までの勤務年限を他科より優遇する措置を打ち出している。
国レベルでは、脳性小児麻痺に対する無過失保障制度を平成19年度中に創設することがすでに決定されている。また、診療報酬についても、産科や小児科を優遇する方針での検討が行われている。このほか、裁判外医療紛争処理(ADR)などにより、医療訴訟圧力を軽減するための検討も進められている。千葉大学でも、文科省の予算で産婦人科医師の卒後教育の重点化のための増員などが行われ、新たな教育指導プログラムを開始した。
診療報酬での優遇制度も検討されている。さらに、産婦人科学会では産婦人科医師に対するドクターフィーの創設を呼びかけている。昨年度新設されたハイリスク管理料などに対しては、病院勤務医師に還元するよう求めてきた。従来、「同一賃金制度」の原則を貫いてきた国立大学病院においても、ドクターフィーを実施する病院が増えてきた。アメリカでは産婦人科医師の減少に対応して、数倍の給与格差をつけてインセンティブとしたそうである。仮に、産婦人科医師数が増加に転じたとしても、悪化した労働環境が一気に改善する見込みはない。これに比べれば、投資はすぐに効果を実施できる。せめて給与面だけでも対応してもらいたいと考えている。
産科医療の抱えている問題は、①マンパワー不足と、②医療システムの欠如の2つに集約される。①には、労働環境・法制度・患者の意識など社会的な問題が関わっており、結局①も②も社会との関わりの中で解決していく必要がある。
産科医療は、reproductionという神秘的で魅惑的な生命のいとなみを対象としており、この分野に興味をもつ学生は多い。しかし、学年が進むにつれて、産科への志望を断ち切る学生が増えてくる。
本稿であげたような産科が抱える社会的な問題にしっかり取り組み、労働環境を改善していくことで産科を躊躇せずに選ぶ研修医が増えてくるものと思う。千葉大学では、先に紹介した教育担当者を中心に教育面での充実も同時に図っている。
おわりに、このような産科側の取り組みに対して、千葉県医師会や千葉市医師会などからも、あたたかい支援をいただいていることに感謝したい。また、周産期施設を有する県内の病院のトップの多くが周産期医療問題を真摯に考えてくださっていることにも、深甚の謝意を表したい。周産期を直接担当していない先生方の産科医療への問題意識・ご意見は、これから周産期医療を選択しようと考えている研修医・学生にとって、最もインパクトのある発言といえる。このような側面でのご支援に深く感謝申し上げる。
(千葉県医師会雑誌掲載予定)