これから医学薬学府に入学する方へのメッセージ、アドバイスを掲載しています
『千葉大学を選んだ理由』
入学前は千葉大学医学部附属病院に理学療法士として勤務しており、臨床研究、特に脳神経内科領域の研究に取り組みたいと考えていました。千葉大学の脳神経内科学教室では、従来、平均生存期間が約3年とされていたPOEMS症候群に対し、ほぼ寛解に導く治療法を確立されており、治療が困難とされる疾患を克服可能な疾患へと変えていく取り組みに強く惹かれました。この教室で学び、研究に貢献したいと考えたことが、千葉大学を選んだ理由です。
『大学院に入学して成長を感じたこと』
私は、「臨床から研究のシーズを見つける視点」を学び、それが自分の成長につながったと感じています。さらに、研究の実施における一連の流れや、アクセプトされやすい論文執筆の方法についても、指導教員の先生から重要なポイントをアドバイスいただき、研究および論文執筆の方向性を適切に修正することができました。また、国際誌の査読を経験する機会にも恵まれ、査読者の視点から論文を評価する方法を学べたことは、非常に貴重な経験となりました。
『仕事と学業の両立について』
在学中の学業としては、臨床業務で蓄積した結果を整理し、それらを症例報告や後方視的研究として論文化できたことが、仕事と学業の両立につながったのではないかと考えています。
最後に、臨床で多くの辛い思いをしている患者さんを目の当たりにしているため、その方々が少しでも希望を持てる未来を作っていけるのが医学研究の役割だと思います。研究に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
4年博士課程 先端医学薬学専攻 令和6年度修了生 黒岩 良太

医学薬学府に入学する皆さんへ
入学の目的や、どんな自分になりたいかは人それぞれだと思います。私は研究者になりたいという思いから、この道を選びました。これから大学院生活を迎える皆さんにとって、私の経験が少しでも参考になれば幸いです。
『入学のきっかけ』
私が医学薬学府を選んだ大きな理由は、「卓越大学院プログラム」の制度でした。研究に専念したい気持ちはありましたが、経済的な不安もありました。その点、このプログラムは大きな支えとなりました。博士課程の学生向けにはいくつかの経済支援プログラムがあるので、進学を考えている方はぜひ調べてみることをおすすめします。
また、学部生の頃から大学院の研究室でアルバイトをしており、実際に研究に触れる機会がありました。この経験は、いわば「試用期間」のようなもので、自分に研究が向いているかを確かめる貴重な機会となりました。そのおかげで、大学院進学を決断する大きな後押しになりました。
『大学院での成長』
大学院では、研究を通じてさまざまな能力を磨くことができました。特に、次のようなスキルが向上したと感じています。
論理的な文章を書く力:研究成果を論文としてまとめることで、論理的な思考や文章作成のスキルが鍛えられました。
国際的な視野と経験:私はフランスの共同研究先の研究室に3回訪れ、実験を行いました。また、国際学会にも参加し、海外の研究者と直接交流する機会を得ました。こうした経験は、自分の研究をより深めるだけでなく、世界の研究者とつながる貴重なチャンスにもなりました。
大学院は、自分の「好き」をとことん追求できる場所です。もちろん、大変なこともありますが、その分、多くの学びと成長があります。研究が好きな人にとっては、きっと充実した時間になるはずです。これからの大学院生活が、皆さんにとって実り多いものになることを願っています。
4年博士課程 先端医学薬学専攻 令和6年度修了生 中谷 一真
千葉大学大学院での4年間を振り返り、最も成長を実感したのは視野の広がりです。2015年に大学を卒業後、2年間の初期研修を経て整形外科医としてキャリアをスタートしました。後期研修では母校の千葉大学整形外科に入局し、臨床研修を終え専門医も取得しました。膝関節を専門とし、困難症例に対する手技の習熟には時間を要しましたが、指導医のおかげで日常診療や手術で困ることはほとんどなくなりました。また、臨床での疑問を研究テーマにし、学会発表の機会も増えていきました。そこで、自分とトップ研究者や著名な医師との違いがどこにあるのかを考えるようになりました。
その後、千葉大学大学院医学薬学府に入学し、佐粧教授、大鳥教授のご指導のもと、千葉県多施設前十字靭帯損傷登録型研究を立ち上げ、軟骨再生や骨折治療促進の基礎研究にも取り組みました。全方位・挑戦的融合イノベーター博士人材養成プロジェクトに採択され、「明らかになっていることと明らかになっていないことを理解し、後者を明らかにする重要性」や「視野を広げることで手法が増えること」を学びました。そして、自分とトップレベルの研究者との違いがここにあると実感しました。
その頃、全方位プロジェクトの一環で新たに始まったダブルメジャー専攻に参加することとなり、佐粧教授の推薦とプロジェクトの支援を受けて、2023年9月から米国The Scripps Research InstituteのMartin Lotz教授の研究室に留学しました。Lotz教授は変形性関節症の研究で世界的に有名で、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析の先駆者です。ここで「変形性関節症における半月板の遺伝子学的病態生理の解明」をテーマに研究を進め、国際学会や全米の研究施設とのオンラインミーティングでも発表しました。また初めての長期海外生活は私たち家族にとって刺激的でとてもいい経験となりました。
2025年3月には帰国し、大学院を修了しますが、今後もこの大学院で培った姿勢を大切にし、研究と臨床の両面で邁進していきたいと考えています。
添付写真は留学先のサンディエゴのコロナドビーチでのサンセット
4年博士課程 先進予防医学共同専攻 令和6年度修了生 坂本 卓弥

私は、熊本大学大学院自然科学教育部から、指導教員(石川勇人教授)の異動に伴い、千葉大学大学院先端創薬科学専攻へ進学しました。千葉大学では、広々とした実験室や充実した実験機器など、研究環境が整っており三年間、不自由なくのびのびと研究に取り組むことができました。また、大学院の授業では、各研究室の先生方がそれぞれの専門分野について講義を行うだけでなく、これまでの研究についてもお話しくださる機会が多くあり、専門性を深めることができました。さらに、他大学の先生方による講義を聴講する機会も多く、幅広い知識を身につけることができました。
博士課程では、研究者として成長するために国際性を磨くことが重要だと考え、私はその点を意識して取り組んできました。千葉大学では、海外の著名な研究者による講演が多く開催されており、世界の最新の研究トレンドについて学ぶ機会も豊富にあります。また、千葉大学のENGINEプログラムの一環として国際学会に参加し、発表を行いました。英語での発表は初めてで、準備には苦労しましたが、異なる文化やバックグラウンドを持つ研究者との交流を通じて新たな視点を得ることができました。このように、国際的な環境の中で研究を深め、世界とつながる機会が豊富にあることは、千葉大学の大きな魅力だと感じています。
後期3年博士課程 先端創薬科学専攻 令和6年度修了生 中嶋 佑太
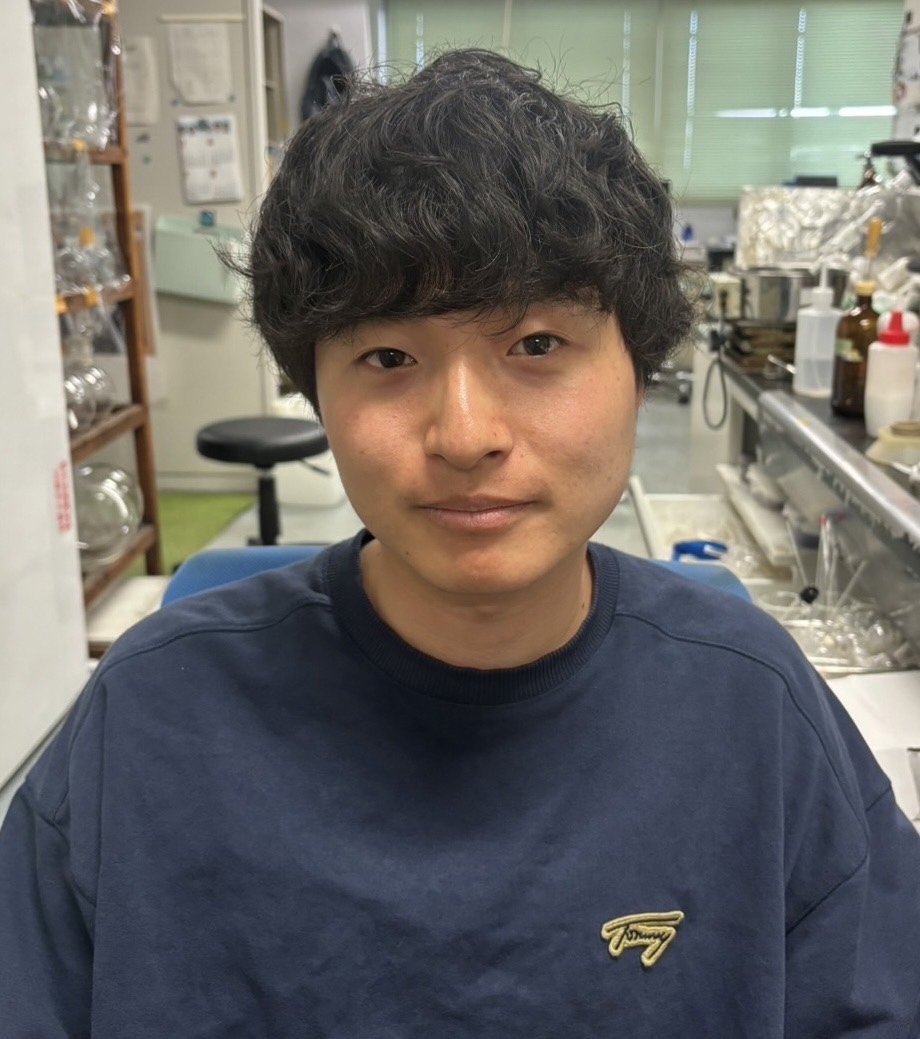
私は、関心のあるテーマにおいて第一人者である教授が率いる研究室で学び、その知識や視点を深めたいと強く思い、千葉大学を選びました。入試の2か月前に研究室の院ゼミに参加し、そこから研究室訪問や院試に向けた試験勉強を始めました。直前からの取り組みで「自分が合格できるのだろうか」という不安でいっぱいでしたが、研究室の先輩方からアドバイスをいただきながら可能な限り努力し、合格することができました。
入学後は、院ゼミに加え、大学外の研究会や学会にも積極的に参加しました。その過程で、分析方法や分析結果を批判的に吟味する習慣が身についたと感じています。授業については、研究に専念できるよう計画を立て、1年生の前半に卒業単位をすべて取得しました。授業の約8割がオンラインだったため、通勤時間を活用して講義を聴講し、レポートの下書きを行い、家族が寝静まった後や早朝の時間帯を活用してレポートを完成させていました。
未就学児の子どもがいる中、夫の協力を得ながら家事・育児と学業の両立に苦労しました。限られた時間を効率的に使い、週末や早朝・夜間を研究に充てるなど、柔軟な工夫を重ねてきました。この経験を通じて、計画力や適応力を磨くことができたと感じています。
修士課程では留学することは叶いませんでしたが、オンラインで代替プログラムを受講し学びを深めました。
研究は一人では行えません。挫折しそうになった時や悩んだ時には、指導してくださる先生方をはじめ、先輩や後輩といった学びの共同体の存在に支えられてきました。研究室での経験は、単なる学びを超えた大きな財産となっています。
この文章が本専攻を目指す方々への参考になれば幸いです。
修士課程 医科学専攻 令和6年度修了生 松村貴与美
関東圏にある数少ない国立大学の薬学部であることから、私は千葉大学を選びました。もともと創薬に興味があったため、前期入試で合格しましたが迷わず薬科学科を選択しました。また、学部1・2年次で薬学に関する普遍科目を幅広く学ぶことが出来るため、自分の興味を明確にした上で研究室を選択することが出来ました。
所属する研究室は製剤工学研究室を選び、研究に魅了に引き込まれていきました。そして、さらに深く研究に取り組むため、来年度からは博士課程に進学する予定です。大学院生活では研究に専念することを最優先に考え、いかに効率よく研究時間を確保するかを意識して生活していました。具体的には、研究室以外の必要な単位は全て院1年次に修得しました。私は、院2年次は知識や手技が定着し、最も自分の実験を推し進めることが出来る時期であると考えています(博士課程に向けての準備としての意味合いもあります)。そのため、授業によって研究時間が削がれることを避けるために、1年次の内に履修を完了しました。
留学についてはオンライン留学制度を活用しました。研究目的を持っての留学は有意義ですが、語学学習のみを目的とした留学は時間の浪費になりかねないと考えたためです。その代わりに、日本国内で開催される英語発表の学会や国際学会に積極的に参加し、英語力の向上を図りました。留学については博士課程在学中に目的を持って行う予定です。
製剤工学研究室で過ごした2年間は非常に充実していました。研究室内の仲間だけでなく、学会に参加するたびに新たな研究仲間が増え、学会参加が楽しみになりました。また、研究室で最も身についたものは「探求心」です。大学院での2年間を通して多くの知識や技術を得ましたが、それに伴い新たな疑問も次々と湧いてきました。そうした疑問に対して感覚的にではなく、論理的に考え、適切な手法で探求する姿勢が身についたと感じています。これにより、より本質的な問題に向き合い、研究を深めることが出来るようになりました。さらに、千葉大学の研究環境は非常に恵まれており、学生の研究を熱心にサポートしてくださる先生方が多くいらっしゃいます。研究の過程で誤った方向に進んでしまった際にも、適切な助言をいただきながら正しい道へと導いていただけるため、安心して研究に取り組むことが出来ます。
最後になりますが、新たに入学される皆さんには、それぞれの目的を持ち、研究に邁進しながら充実した学生生活を送っていただきたいと思います。皆さんにとって、有意義な2年間となることを心より願っています。
修士課程 総合薬品科学専攻 令和6年度修了生 藤本泰輝